
 |








旭川市民劇場@net
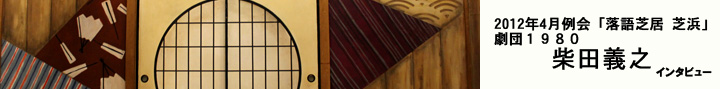
第回 [PR](2026.01.09)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第5回 柴田義之さんインタビュー(後編)(2012.06.04)
| 2012年4月例会「落語芝居 芝浜」劇団1980の柴田義之さんへのインタビュー。 |
- 海外での公演
───劇団1980はブラジル、ルーマニア、モルドバ、パラグアイなど海外での公演もたくさん行っているとのことですが、海外公演のとき言葉はどうしているのですか?
全部日本語です。字幕を出しています。───日本のお国事情が反映された内容の作品も多いですが、意味は伝わるのでしょうか。
わかりますね。やっぱりラテンの人っていうのは、韓国も「東洋のラテン」と云われるくらいですけど、肌で感じます。「ええじゃないか」で最後にみんながバーッと撃ち殺されていくシーンなんか、やっぱりみんな、涙流して、すごい感動してましたね。
演劇っていうのは、政治とか、また文学とか、そういうのと違って、ワンシーン見せただけで…、たとえば、メシの食い方だとか、そういうもので、その国のある面がパッと見えたりする瞬間があるじゃないですか。
僕らが「素劇 あゝ東京行進曲」をブラジルでやったときなんか、ブラジル人は、日本人はみんな「神風」とか、戦争を信じ切ってやっていたんだと思ってるから、一般の庶民はもっとずっと戦争というものを冷ややかに受け止めていたということに驚いたみたいでした。───海外での公演を行うようになったきっかけというのは?
95年に初めてですね、ルーマニアのシビウっていうところで、演劇祭(シビウ演劇祭第二回目)がありまして、今はもうすごい世界的な演劇祭になって、アヴィニョン演劇祭とエディンバラ演劇祭と並んで、ヨーロッパ三大演劇祭って云われてるんですけど、その当時はまだ小さな演劇祭だったんですよ。
1989年にルーマニア革命というのがあって、チャウシェスクが倒れて、まだ革命から時をそんなに経てないルーマニアで、民間の青年たちが、一生懸命集まって「演劇祭をやろう」ってことになったんです。
僕らがその2年前に、東京国際演劇祭に正式招待で呼ばれて出たので、そのときのすごい立派なパンフレットを見て、それでそういうパンフレットがいろんな国のフェスティバルのディレクターなどに配られるんですが、それを見て「1980を日本から呼びたい」っていうんで、僕らが初めて、そのときは日本の劇団は僕らだけで、「謎解き 河内十人斬り」という演目で、行ったんですね。
そしたらなんと、そのときに、僕のところにその招待状が来たのが12月の20日くらいだったんです。
でも彼らは、夏頃から招待状を日本に出してたんです。だけど、その劇団名を間違えいて。1854…とかなんとか、ヨーロッパに革命があった年の名前で出したもんだから、「そういう劇団はないぞ」って郵便が行ったり来たりしてる間に半年経って。で、横浜がルーマニアと仲の良い都市なので、横浜の文化局みたいなところにその招待状が来て、それでやっと僕のところに来て。
でも、もう文化庁の助成も締め切ってるし、国際交流基金もダメだから、「こんなの行けないな」と思って、置いといたんですよ。そしたら藤田傳が、「これ何だ」って云うから、これはこうこうこういうもんで、僕は行かないつもりでいますって云ったら、藤田傳が「こういうのはァ、誘われたら行くもんだヨ」って寅さんみたいなこと云って(笑い)。
それで、僕らはそのあと、お金を一生懸命作ってですね、向こうからお金借りたり色んなことして、行ったんですよ。
それが最初だったんですけど、そのあとはもう毎年、色んな劇団が行って、公演をやっています。───海外での公演となると、やはりアクシデントも多かったりするのでしょうか。
アクシデントばっかりですよ!僕らの常識が、向こうでは全然常識じゃないですから。
バスなんかね、すごいですよ。ブラジルなんか、もうコーディネーターの人が行ってバス会社にバスを手配するってなったら、「どのバス出すんですか?」「これを出します」って云ったらそれを写真に撮って、「誰が運転するんですか?」「この人です」って、その人の写真も撮って持って来ないと、もし当日もっと儲かるようなイイ話が入ったら、そっちの方にみんな行っちゃうわけです。
日本みたいに「依頼すれば来る」と思ってると、とんでもないことになっちゃう。
海外公演は、韓国も何回か行きましたね。韓国のアルコ芸術劇場っていう国立の劇場で「ええじゃないか」の公演を十日間やったんですね。それでもう、連日チケットが売り切れて。日本以外ではウケてるんですけどね(笑い)。 - 「コミュニケーションの壁」を超えて
この間、二人芝居をやったんですよ。
「漫才芝居」といって、モルドバ(旧ソビエト連邦の国家の一つ)の女優さんと、僕が「言葉が通じない」っていう芝居。これは、字幕なしで、日本人は僕の反応で、彼女の云っていることを推測するしかないんですね。
これを今度は、五月にルーマニア、モルドバに持って行ってやるんです。今度は逆に僕の言葉が通じない、という状況になる。藤田傳が書いた脚本で、脚本にしたら17分くらいのものなんですけど…
まず、バス停があって、そのバス停に女の人が座っている。
僕が鞄を持っていて、鞄をポンと置いたら、それが当たったとか当たらないとか云って、ふと見たら外人なわけですよ。で「あっ、外人だ」と思って見たら、その女が「あんた私のお尻を触ったでしょう」とか「私の物を盗んだんじゃないの」とか云う。それを「そうじゃない、そうじゃない」って云って、一生懸命弁解するわけです。
そのうちに、「じゃあ鞄の中を見せなさいよ」と女が云う。
そうしたら、タキシードが出てくるわけです。それで、「これは何だ」って云ったら、「俺は、実は、中学を卒業して東京に行って、四十年間土方をして働いていた。ビルを建てたり橋を造ったりして、やったんだ、日本を作ったんだ」と。「それで、二年前に怪我をして、入院したら、隣のベッドにマジシャンがいて、その人にマジックを教えてもらって、今は養老院でボランティアをやっているんだ」。これを、身振り手振りで云うわけです。
そしたら、マジックでパッと花を出したら、それが萩の花なんですよ。
その花を見て、女の人が、自分のおばあさんが若い時分にシベリアのアングレンというところにいて、モルドバっていう国はルーマニアの一部だったんだけど、戦争が終わったときに分割されて、きのうまでのモルドバは全部無くなってしまう、今日からは言葉は全部ロシア語を使えと云われて、モルドバ語を使えたり読んだり出来る人は、みんなアングレンというところにある収容所に家族ごと幽閉された。そのときに、おばあさんが日本兵と出会って、その日本兵から萩の花をもらって、「私は、その花を探しに来ているんだ」って、こう、云うわけですよ。
「これは秋の花だから、今はもう冬だから、ない」って男が云う。
「天国のおばあさんにこの花をプレゼントするよ」と、渡した瞬間にバスが来て、「あなたの乗って行くバスはあれだ。俺はあっちに乗って行く」。そうして、バスのクラクションが鳴って、それがだんだん音楽になって終わる…という。
「バス停」というタイトルの脚本です。これが、実際に演じると50分かかるんですよね。
「二年前」なんて説明するのだけでも、大変。
脚本には「二年前に」って書いてあるけれども、どうしたらいいかなあ…「二年」…「二年」…
ってわかんないから、だから、ガーンと鐘が鳴って、ワーッとクリスマスになって、春になって夏になってもう一回クリスマスになってワーッ、とか。そういうふうに。
2010年にモルドバで公演をやったときに、僕らずっとその女優さんと仲良くて、バスに乗っているときに女優さんが藤田傳に「わたしのために一人芝居を書いてよ」と云ったんですよ。そうしたら藤田が「俺は女の一人芝居は書けないけど、柴田と二人で言葉が通じない同士の芝居、というのをやってみようよ」って、それから始まったんですよ。
慶応大学のコミュニケーションを研究している人が、このビデオを題材にして、外国人とのコミュニケーションの授業に使いたい、なんて云われたりもして。
演出も藤田傳なんですけど、何にもしなかったですね。ただこう笑って見てるだけ。
ただひとこと、「とにかく大汗をかいてくれ」と。相手にわかってもらうために、どれだけ汗をかくか。
やる前にいっぱい水を飲んでくれって云われたんだけど、水なんか飲まなくたってすごい汗かいて。観てる人はわかるんですよね、観てる人は僕の反応で、彼女が何を云ってるかわかってくる。だんだん、僕と一体化して。───「大汗をかいてくれ」というのは、「コミュニケーションとは、相手のために汗をかくことだ」ということですよね。
まさにそうです。やっぱり、いちばんの壁は言葉の壁だから。
そういうコミュニケーションの壁を、人はどんなふうに乗り越えて行くのか、っていうのがテーマだっつって…偉そうに云ってますけど(笑い)。
だから、僕も最初は「言葉」がテーマだと思ってやっていたんです。
で、稽古をやっているうちに、「これは、相手を求め合っている人間同士がやってる芝居なんだ」って。
知らない国に来てバス停にぽつんといる女、それから、四十年間も土方をやって今ボランティアで養老院をまわっている家族もない男。お互いが、本当に「知り合いたい」と思っているから、成り立つんで。
だんだん、そうなんだっていうことに、向こうの女優さんも、僕も、気がついていって、藤田はニコニコ笑いながら「まあ、俺は最初からそう思ってた」って(笑い)。僕も最初、やるまでは、こんなのが面白いのかどうか、よくわかんなかったんですけど、本当にいい経験でしたね。 - 次回「素劇 あゝ東京行進曲」?
FlipClip 「素劇 あゝ東京行進曲」2004年ブラジル公演の様子(動画)───劇団1980の取り扱う題材は幅広いですよね。海外の人との共演、落語、戦争や市民伝…
是非次回は「素劇 あゝ東京行進曲」(「東京行進曲」を歌った昭和の歌姫・佐藤千夜子の生涯を描いた劇団1980の舞台)で旭川市民劇場へ、というお話がありましたが。
この公演から帰ったら、またすぐ稽古するんですよ。長野の高校生に6月に「東京行進曲」を見せるために。
鑑賞会も、僕たちが80年の初演の頃とか、1993年にやった頃とかには、佐藤小夜子さんのことを知っている人が7割も8割もいたわけですよ。でももう今は3割ぐらいしかいない。
本当は、この芝居のテーマっていうのは、二十世紀という時代に、男性社会の中で戦っていった女性の芸術家の話にしたいし、昭和という時代を、戦争とか色んなものに翻弄されて生きた庶民の歴史を歌で綴る、というふうにしたいんですよ。
ブラジルの人たちが、佐藤小夜子のことも全然知らないし、歌も知らない、まったく知らないんだけど、一人の女性の芸術家がこんなふうに生きて死んだんだ、っていうことにすごく感動したんですね。この芝居の持っているテーマはそういうもので、もしかして佐藤小夜子のことを知らない人がどんどん増えた方が、純粋にね、この芝居の持つテーマが伝わるんではないかな、と思って。
だから、今度高校生に向けてやるときに、もっとそういうものに近づけたいなと。ノスタルジックなものではなくて、もっとこう、強く訴えていくような芝居にしたいなと思って作り変えているんで。
もちろん「劇中の曲、全部知ってたわよ!」っていうの、それはそれで楽しみ方としていいんです。ただ、今後そういう方たちが減って行く中で、この芝居が持っているエネルギーみたいなものをもっとこう燃やさないといけない、燃やし続けるにはどうしたらいいかな、と思って。
関矢さん(演出の関矢幸雄さん)が一生かけて考えた「素劇」ですからね。───「東京行進曲」は、「素劇」の名の通り、セットとしての舞台装置がまったく登場しないんですよね。黒い箱と白い数本のヒモだけで山並み、駅、学校、戦艦、戦後の焼け野原といった舞台が、めまぐるしく展開されていく。
ものすごく、ヒューマンだと思うんですよね。アイディアだけじゃなく。
すごい速さですよ。もう、スポーツですからね。僕らも、演劇やってるって感じしませんからね(笑い)。箱を積むにも、角がずれない、音もしない。あの練習だけでも、すごいするわけですよ。一つの箱が4キロちょっとあって、結構重いんです。で、高さがちょうど腰に悪いくらいの(笑い)。
あの箱とヒモだけで、なんでも出来るんですよね。でも、いちばんすごいのは、観ている人の想像力。観る人たちがやっぱり、「あっ、あれになってる」とか「あっちでもあんなことやってる」とか、いろんなものを発見してくれる。
以前は黒の背景に黒の衣裳でやっていたんですが、田舎風の色合いの、バラバラの色の衣裳に変わりました。
黒でやるということは、ある意味でクローズアップだから「これを見ろ」っていうことにになるんじゃないか、と関矢さんが最近思ったんです。だから、色がいろんな色、バラバラになることによって、観客が自分の選択肢みたいなものを…黒だと、演出家が「ここを見てほしい」ということになってしまうんじゃないかと。照明も少し変えたりして。
そういうことをしながら、あまりクローズアップしないで、もっと云えば、観ている人が発見出来るような余地を残したい、というのが、関矢さんの今の素劇論ですね。前は黒と白の対比で行こうとしたんだけど「そうじゃない」という。
どんどん進化する…87才のおじいさんですから。
人間はどこまで進化するのか、と思いながら、僕ら見てますね。「この人、死なないんじゃないか」とか(笑い)。
未だにどんどんどんどん進化して行って、「もっと違うものを作りたい」って。
稽古場でも云ってますよ、関矢さん。「柴田くーん、人間は順番通りじゃないよ!」って。
僕ら、基本的には、仕事というよりも「面白いからやってる」というところがあります。
だから、演劇に出会って、こうして市民劇場や鑑賞会をまわって、面白いって云ってもらって、それでなおかつお金までいただいて。すばらしい仕事だなって思いますね。
僕らは、結局、勝手に芝居をやったわけじゃないですか。最初は誰からも頼まれたわけじゃない。
誰かが「面白い」とか「感動した」と云った瞬間に、はじめて価値が生まれるんであって、そうでなければずっと昔のまんま。勝手にやっただけですから。
だけど、こうして市民劇場に来て、こうして芝居をやって、「よかったよ」とか「また来てね」とか云って手を握られた瞬間に、ポッと価値が生まれる、というような感じがするんです。───さらに進化する「東京行進曲」で、また旭川市民劇場に来ていただく日を楽しみにしています。
本日はどうも、ありがとうございました。
(取材:2014年4月17日旭川市民文化会館 インタビュー構成:淺井)PR運用協力 : Ninja Tools | 忍者ブログ | [PR]
